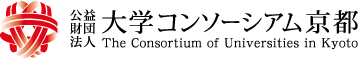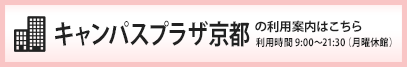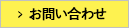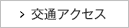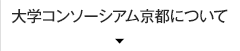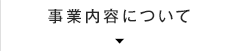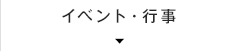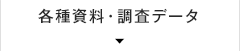令和7年度 学生と地域をつなぐ学まちコラボ事業の取組をご紹介します。
大学・学生と地域が『コラボ』して京都のまちづくりや地域の活性化に取り組む企画・事業を募集し、助成支援を行う“学まちコラボ事業”。
今年度採択団体の取組をお知らせします!!
【活動紹介①】立命館大学 『きぬがさ農園Kreis』
8/20日(水)、立命館大学衣笠キャンパスで「Kreis地域食堂」が開催され、見学してきました!
2020年、コロナ禍の中で立ち上がった「きぬがさ農園Kreis」は、地域と連携しながら野菜作りを行う学生団体です。学生約70名が中心となり、地域の方と落ち葉で腐葉土を作るところから始め、収穫した野菜は学食や地域に届けるなど、地産地消と地域交流、SDGsを意識した活動を行っています。
今回が初開催となった「Kreis地域食堂」では、自分たちで育てた野菜を使ったカレーをふるまい、学生20名、地域の方15名が参加しました。 「一人で食事をする高齢者や子どもが多い地域だからこそ、みんなで囲めるあたたかい食卓を作りたかった」と、代表の篠原茉凛さんは話します。
広報活動としては、近隣地区へのポスター配布や農園前に設置した掲示板を活用。農園が等持院前の散歩コースにあるため、自然と地域の方の目に留まり、来場のきっかけになったそうです。 イベント準備で一番大変だったのは、野菜の収穫量が読めなかったこと。どの年代が来てくれるのか分からず不安もあったそうですが、実際には多くの方が足を運んでくれたことで安心したと言います。 また、これまでは夏季休暇で大学の食堂が閉まると収穫した野菜の提供先に困るという課題がありましたが、今回のイベントを通して多くの夏野菜を活用できたのも大きな成果です。
今後について篠原さんは、「農園に来ていただいて、実際に学生と楽しくお話する機会を持つことができれば嬉しい。農業の楽しさやSDGsへの意識がこの活動を通して自然に広がっていったら」と話してくれました。
最後に、取材に訪れた私たちも、採れたて野菜のカレーをごちそうになりました。新鮮な野菜の味わいと、活動への想いがぎゅっと詰まった一皿。とても美味しかったです。
ごちそうさまでした!
活動状況は、↓でご確認ください。 https://www.instagram.com/kinugasanoen__kreis/




【活動紹介②】立命館大学 『嵐電沿線フジバカマプロジェクト 学生チーム』
10月10日(金)~19日(日)まで嵐電嵐山駅構内で「フジバカマ湯」が開催されました。イベント前日の9日(木)に、準備の様子を取材しました!
※フジバカマとは? 秋に白から淡い紫色の花を咲かせる香り高い花。平安時代には香袋に使われ、現在では渡り蝶「アサギマダラ」を呼ぶ花として親しまれています。
2021年に始まったフジバカマプロジェクトは、学生を中心に嵐電や立命館大学の教職員、地域の方々の協力のもとで、年間を通じてフジバカマの保全活動を行っています。 春にはフジバカマの苗を植え、夏に育て、秋に花を咲かせます。地域の小学生やボランティアも参加し、育てる過程を通して交流を深めています。
「フジバカマ湯」は、プロジェクト初期から続くイベントで、フジバカマの魅力を多くの人に知ってもらいたいという思いから始まりました。観光地・嵐山での開催を通じて、地域の方や観光客に活動を広く発信しています。
準備では、嵐電や造園業者と連携し、資材運搬や設営を調整。地域の方々にも、挿し芽や定植作業に参加してもらうなど、地域全体で協力し合いながら進められました。
代表の飯沼さんは「フジバカマの栽培で一番大変なのは水やりです」と話します。 フジバカマは水を好む植物で、毎日の水やりが欠かせません。今年は支援金を活用して灌水設備を導入し、自動で水やりが行えるようになりましたが、夏休み中も学生たちが交代で水やりを続けました。その努力の成果もあり、今年は花付きが良く、立派に育ったそうです。
丈夫なフジバカマを育てることは、地域づくりにもつながります。葉が元気に育てば、足湯や匂い袋作りなどのイベントも充実し、地域の方との交流もさらに広がります。実際に、花を見に訪れた地域の方や学生、教職員との会話が生まれるなど、フジバカマが人と人をつなぐ存在となっています。
今後も「守り、育てる」という思いを大切にしながら、地域とともに活動を広げていきたいとのことです。 後日談として、渡り蝶「アサギマダラ」が衣笠キャンパスのフジバカマにも飛んできたようです! 今後も、フジバカマを通した保全活動の広がりが楽しみです。
活動状況は、↓でご確認ください。 https://www.instagram.com/fujibakama.r/