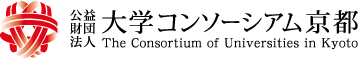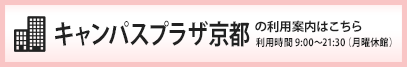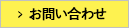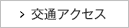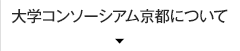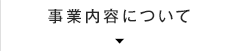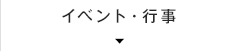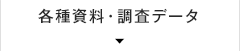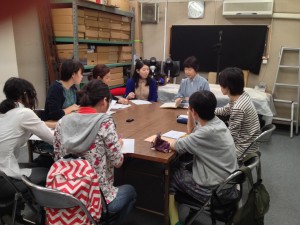ここでは、二条城×同志社大学『世界遺産PBL講座~O2Oマーケティングによる地域活性化』(担当:多田実先生)の授業の様子や受講生の活動をレポートしていきます。
二条城及びその周辺でのフィールドワーク
7月12日(日)の授業では、二条城とその周辺地域でのフィールドワーク及び、二条城の職員へのインタビューを行いました。
多田先生のクラスでは、調査、分析、クラウドファンディングの検討等のマーケティング戦略を担当する「チームM」が2グループ、SNS等を活用した広報戦略を担当する「チームA」、動画を制作し、YouTubeでの公開を目指す「チームY」の4チームで活動しております。今回のワークもこの4つのチームに分かれて活動しました。
当日は13時に集合し、まず、チームごとに1時間半ほど二条城周辺のフィールドワークを行いました。
チームAは、二条城に隣接する神泉苑を調査しました。神泉苑では、その歴史や文化財に関する調査、二条城との関係などを確認しました。
チームYでは、二条城の周りを調査し、周辺に小中学校があることから、周辺地域の児童・生徒に向けて、二条城の良さや興味を持ってもらうアプローチも効果的ではないかなどの意見が出ました。
チームMの2チームは、二条城周辺のお店の調査を行い、うち1チームは三条商店街を見てまわりました。三条商店街では、観光客よりも地元住民に重きを置いたお店が多いことなどの発見がありました。


周辺地域でフィールドワークの後は、引き続きチームに分かれて、約90分間二条城内のフィールドワークを行いました。城内のフィールドワークでは、案内パンフレットは多言語対応している中で、設置されている立て看板は日本語のみのものが多く、これを多言語かすることによって、より二条城の魅力を伝えられるのではないかといった発見や、歴史的意義のある二条城に合うキャッチコピー考案の有用性など多くの発見や気づきがありました。


フィールドワーク終了後は、京都市文化市民局元離宮二条城事務所の後藤玉樹課長にインタビューを行いました。インタビューでは、これまで二条城で行われてきたイベントや、文化財である故の制限事項や苦労などについて質問が行われました。また、具体的な企画案についても意見交換を行うなど、学生が主体となった活発なやり取りが行われました。

今後は夏休みの自主活動を経て、提案の具体化を図っていきます。
ゲスト講師:河尻亨一氏による講義
河尻亨一氏(銀河ライター主宰/東北芸術工科大学客員教授)をゲスト講師に招いて、広告・プロモーションに関する講義が行われました。
河尻亨一氏は、広告クリエイティブ専門の編集者です。多田先生のクラスは、オンラインを活用したプロモーションによる二条城への観光客誘致やイベントの活性化をテーマにしているため、今後のプロモーションの企画を練るにあたって、非常に参考になる講義を行っていただきました。
河尻氏は、毎年、フランス・カンヌで開催される、広告、コミュニケーション、プロモーションに関するコンペティションの祭典「カンヌライオンズ 国際クリエイティビティ・フェスティバル」を取材されております。今年も6月下旬に開催され、そこでの取材された内容も交えて、昨今のプロモーションの潮流や、企画する際のヒントについてお話をいただきました。講義の中では、実際にカンヌライオンズの受賞作品を紹介しながら、その中でどのようにO2Oという手法が活用されているかなど、具体的な事例も交えた解説もありました。
河尻氏からは、O2Oを活用したプロモーションでは、「強い共感をもたらす、シンプルでかつ骨太なアイデアとストーリー」が重要であること、「O2Oはすでに日常生活に取り入れられている(「O=O」状態になっている)ので、それほど難しく考える必要がないこと」など、今後プロジェクトを進めていくうえでの重要な示唆もいただきました。


河尻氏の講義のあとは、グループに分かれ、講義で感じたことや学んだことを共有して深め、グループごとに質疑応答が行われました。質疑応答では、「ゆるキャラ」の活用の是非などについての意見交換も行われました。
次回の7月12日(日)の授業では、二条城を訪れ、フィールドワークやインタビューに挑戦します。
二条城についての学習
6月11日(木)、二条城を舞台に活動を展開する同志社大学の多田先生の授業が行われました。多田先生のクラスの初回授業は、5月30日(土)の他クラスと合同の開講式・全体オリエンテーションだったため、単独で行う授業は今回が初めてでした。
多田先生の授業のテーマは、「O2Oマーケティングの手法から地域活性化の『仕掛け』を作り出す」こと。O2Oとは、Online to Offlineの略で、ソーシャルメディアなどオンライン上(Web上)でのプロモーションを活用して、それに関連する商品やサービスを販売・提供する実在の店舗等(オフライン)に消費者を誘導するマーケティング手法のことを指します。
二条城は、1603年の徳川家康による築城以来の20年間に渡る本格修理事業の真っ最中で、修理費用の一部を寄付や様々なイベント事業での収益で賄うことを目指しています。O2Oの手法を用いて、いかに二条城への関心を高めて来場者や各種イベントへの参加者を増やし、修理費に充てる収益を得ることができる提案を行うことが、本クラスが挑む課題の一つです。
今回の授業では、二条城についての理解を深めるため、元離宮二条城事務所の梅林課長を講師に迎え講義が行われました。梅林課長からは、二条城の歴史や場内にある文化財の紹介、国内外からの二条城の評価などご紹介いただいた後、二条城が取り組んでいる「世界遺産・二条城MICEプラン」ご説明いただきました。MICEとは、「Meeting」、「Incentive」、「Convention」、「Exhibition / Event」の頭文字からなる造語です。歴史的価値の高い世界遺産・二条城をMICEの会場として提供することで、二条城や京都の魅力や文化財の価値を広く発信し、併せて収益の獲得を目指しています。これまでに実施してきたイベントや、イベント実施に当たって生じる文化財であるがゆえの苦労などについてお話いただきました。


講義の後は、4グループに分かれてグループワークを実施。講義の内容をグループで深めるとともに、梅林課長への質問事項やMICEの可能性についての意見交換等が行われました。